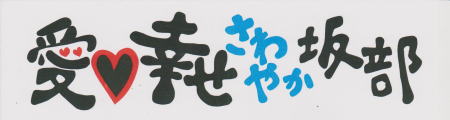本間翁坤徳之碑献花式
2025年3月20日 本間賢三翁「観理坤(こん)徳之碑」献花式が行われました。
1)本間賢三翁の紹介を下記しました。
江戸末期、旧榛原町の坂部と細江地区では 、洪水と干ばつがたびたび起こり、当時の農民達は大変な苦労をしていました。坂部の「本間賢三」、細江の「加藤孫左衛門」と「西谷傳蔵(でんぞう)」、の3人は、対策を話し合いました。 そして、たびたび氾濫する「坂口谷川」には、川幅の拡幅を行うことにしました。 また、「大井川」から水を引き、干ばつに備える為の水路を作ることにしました。3人は村人を説得し、皆から集めたお金を元に、「坂口谷川の工事」は行われ、明治4年(1871年)に完成しました。
一方、大井川から水を引く為には、吉田町側から坂部側までの間に、長さ300メートルの隧道(トンネル)工事が必要でした。当時は手掘りのため、困難と多くの費用が掛かり、皆が出し合ったお金は足りなくなってしまいました。 三人は、私財を売り資金を作り、大変な苦労と努力で工事を続け、明治9年(1876年)に用水路は完成しました。
現在この用水路は、「本間用水跡」として市の文化財に指定されています。
本間賢三は、治水事業の他に、地元の発展にも尽力をしました。本間家墓所の脇には、賢三の業績を称える「本間翁の記念碑」が建立されています。
以上、まきのはら活性化センターの「牧之原市観光案内」記事からの抜粋です。
2)また、坤徳之碑の表面記載文を紹介します。
本間賢三は天保八年(一八三七年)本間栄五郎の長男として坂部に生まれ 剣の道を極め免許皆伝を受け 剣客名を観理と号した
明治二年の頃 牧之原の開墾に移住してきた武士たちとの間に まくさ場の使用をめぐる紛争が起こり 賢三は死を覚悟して談判を重ね 坂部村まくさ場(後の村有林)の永代借地権を確保した
明治八~九年 多くの人々の協力を得て 用水路の難工事を行い 百ヘクタール余の田に大井川の水を引いた「本間用水」と呼ばれたこの用水路はその後の改修もあり 今でも豊かな水を田に注いでいる
郷土の発展に尽くした賢三は 明治四十四年九月七十五歳で没した
賢三翁の遺徳は 没後も脈々と郷土に受けつがれてきた 私たち坂部区民は先人の意思・気風を継ぎ郷土の発展に尽くしたい
平成二十二年三月吉日
本間賢三翁没後百年祭実行委員会